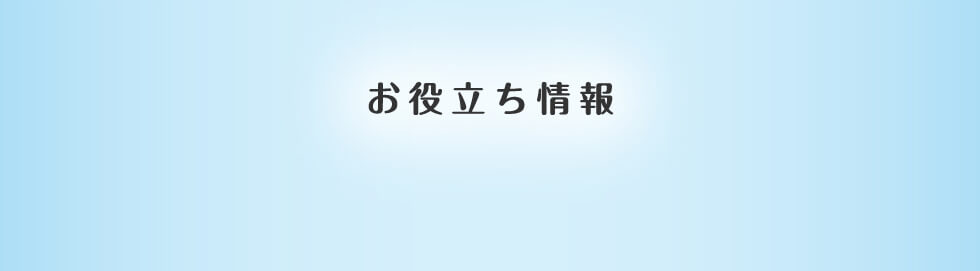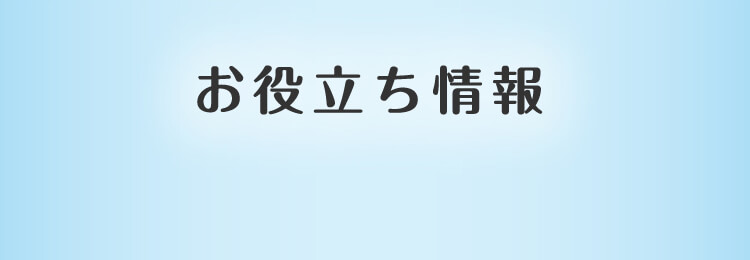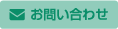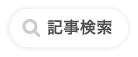
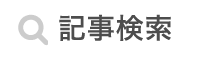
トップページへもどる
手続き・老齢年金.jpg)
年金受給者が死亡した場合に必ず必要となる手続は「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出です。併せて「未支給年金請求書」の提出が必要となる場合があります。
<遺族年金について>
老齢厚生年金や障害厚生年金の受給者が死亡した場合は、遺族(配偶者、子、父母、孫)に遺族厚生年金を受ける権利が発生することがあります。
受けていた年金の種別に関わらず、遺族に18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にあるかまたは20歳未満で1・2級の障害のある子が含まれる場合は、遺族基礎年金を受ける権利が発生することがあります。
手続
・提出する人は、同居の親族など戸籍の死亡の届出義務者とされています。(日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合、死亡から7日以内に戸籍の死亡の届出を行えば、年金の死亡届は不要となります。)
・提出先は、日本年金機構です。最寄りの年金事務所が窓口となります。
・提出期限は死亡したときから14日以内とされています。
・用意する書類は、「年金証書」、「死亡診断書など死亡を明らかにする書類」です。
留意事項
年金は月単位で支払われ、受給者が死亡した場合は死亡した月までの分が支給されます。死亡の届出が遅れると、死亡の翌月以降の分が支払われる可能性があり、死亡の翌月以降分が支払われた場合、後で年金を返さなければならない場合があります。
手続
・被保険者の死亡の手続は、加入している制度や被保険者の種別により異なります。
・国民年金の第一号被保険者が死亡した場合は、住民票や国民健康保険の死亡の手続と同時に、市(区)役所または町村役場の窓口で行います。手続を行う人は、同居の親族など戸籍の死亡の届出義務者です。
・国民年金の第三号被保険者(厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者)が死亡した場合は、厚生年金保険の事業主や共済組合が手続を行います。
・厚生年金保険の被保険者が死亡した場合は、事業主や共済組合等が手続を行います。
年金は年6回偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支払われますが、支払われる額は、支払月の前2カ月分が、後払いされます。 したがって、6月に支払われる額は、4月分と5月分となります。このため、年金受給者が死亡した場合、支払われていない年金が発生することとなります。例えば5月に死亡した場合、4月分と5月分が支払われていないことになります。この未払い分は、「未支給の年金」として、一定の要件を満たす遺族に支払われます。
<請求できる人>
未支給の年金を請求できる遺族は、死亡した受給者と生計を同じくしていた(同居、仕送りなど)配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、他の三親等以内の親族です。ここに列挙した順番に順位が決められており、先順位者がいる場合は、後順位者は請求できません。同一順位の遺族が複数いる場合は、代表で1名が請求します。
<手続について>
死亡した人が年金を受ける権利を有しながら請求する前に死亡した場合は、いったん死亡した人の年金を請求する手続が行われます。未支給年金の請求は、基本的に受給権者死亡届と同時に行われます。
用意する書類は、親族関係及び生計同一を証明するものです。(戸籍謄本、住民票、仕送りの状況など)
過払いの発生や未支給年金の関係を考慮して、あらかじめ死亡届を提出する人を決めておくとよいでしょう。
留意事項<年金と相続権>
年金を受ける権利は受給者に固有のもので、親族であっても他人に譲り渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。未支給の年金は、一定の要件に基づき給付として遺族に支払われるものであり、相続財産として支払われるものではありません。したがって要件を満たす遺族がない場合は、相続人が設定されていても支払われません。なお、すでに支払われた年金は財産として相続対象となります。
手続き・老齢年金.jpg)
トップページへもどる